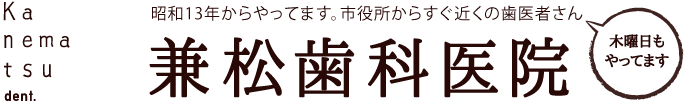人にとっての水は無くてはならないもの。
この当然のことが案外、日常生活の中において軽んじられているようです。
今回は、健康・アンチエイジング面において「水」のもつ重要性についてお話します。

成人の場合、人の体重の約6割を水分が占めています。
水は、生命現象に必要不可欠であり、体内を循環して必要な栄養素や酸素を運び、不要な老廃物を体外に排出する役割を担っています。
人は1日どのくらいの水分を摂取すべきか?
米国のアンチエイジング医学専門医は毎日、体重1kgにつき30mlの水を飲むことが健康維持のために必要と述べています。計算すると成人男性の場合は、約2Lの水が毎日必要になります。
お茶やコーヒーは、利尿作用があるので、これらは水分摂取量には入れません。

どのような水が健康によいのでしょう?
日本の水道水は、基本的に微生物や重金属の汚染についてはクリアされていますが、微生物を除去する目的にて塩素を添加しています。低濃度とはいえ、消毒剤をそのまま体にとりこむのは少し疑問が残ります。
「水素水」と呼ばれる水が話題になっていますが、動物実験において抗酸化効果と酸化ストレス障害の軽減効果が確認されています。
「アルカリイオン水」については歴史も長く、飲むのには適した水といえます。
「クラスター」と呼ばれる水分子の集合体にも注目が集まっています。クラスターが小さい方が細胞への出入りがしやすく、代謝を活発にするのではないかといわれています。
「ミネラルウォーター」の硬度は溶在している、カルシウムやマグネシウムといったミネラルの総量で決まります。カルシウムの多いものは動脈硬化予防効果や骨の健康に良いとされているますが、便秘を招くなどのデメリットもあります。一方、マグネシウムを多く含むものには、血圧降下作用や便秘の改善などの働きがあります。
腎臓疾患や心不全の患者さん、体が冷えやすい人やむくみやすい人など、水分摂取を控えたよい人もいます。 また、漢方では、「水毒」という考えがあり、水の飲みすぎは体に良くないといいます。
健康維持、アンチエイジングのためには、自分の体に合った水をみつけることと体調に合わせた摂取水分量を決めることが極めて重要です。