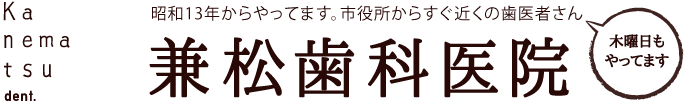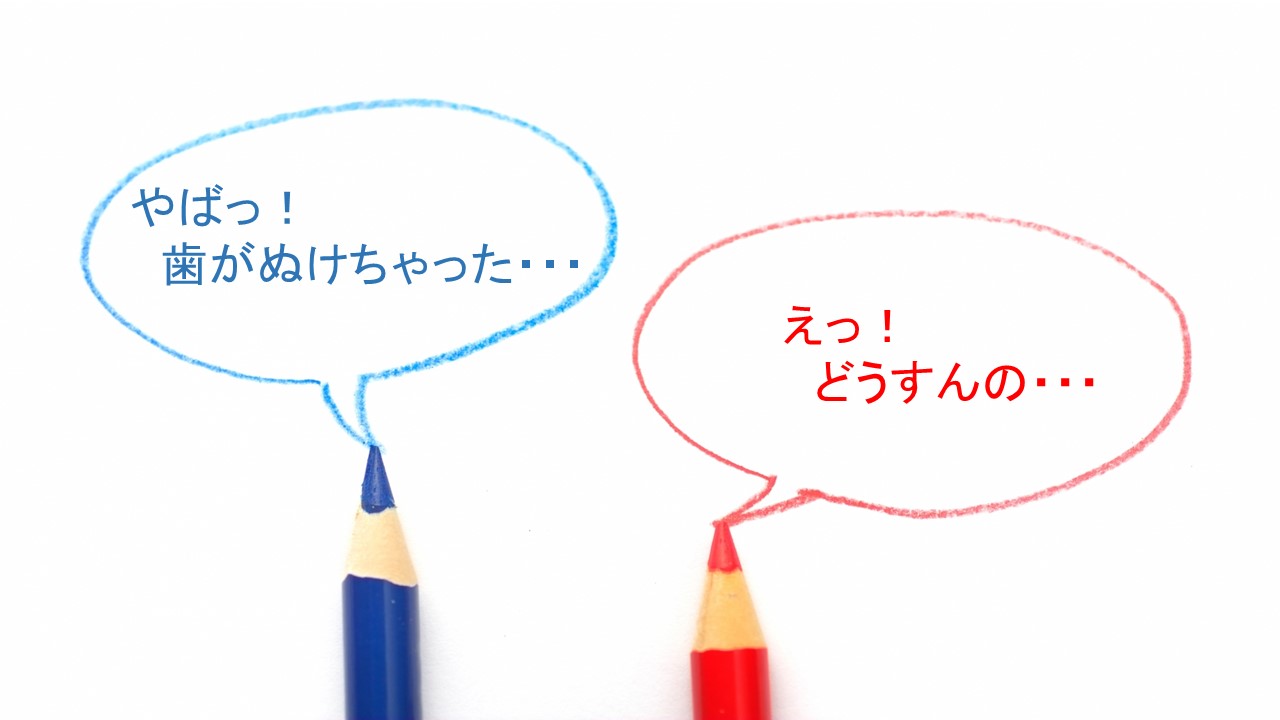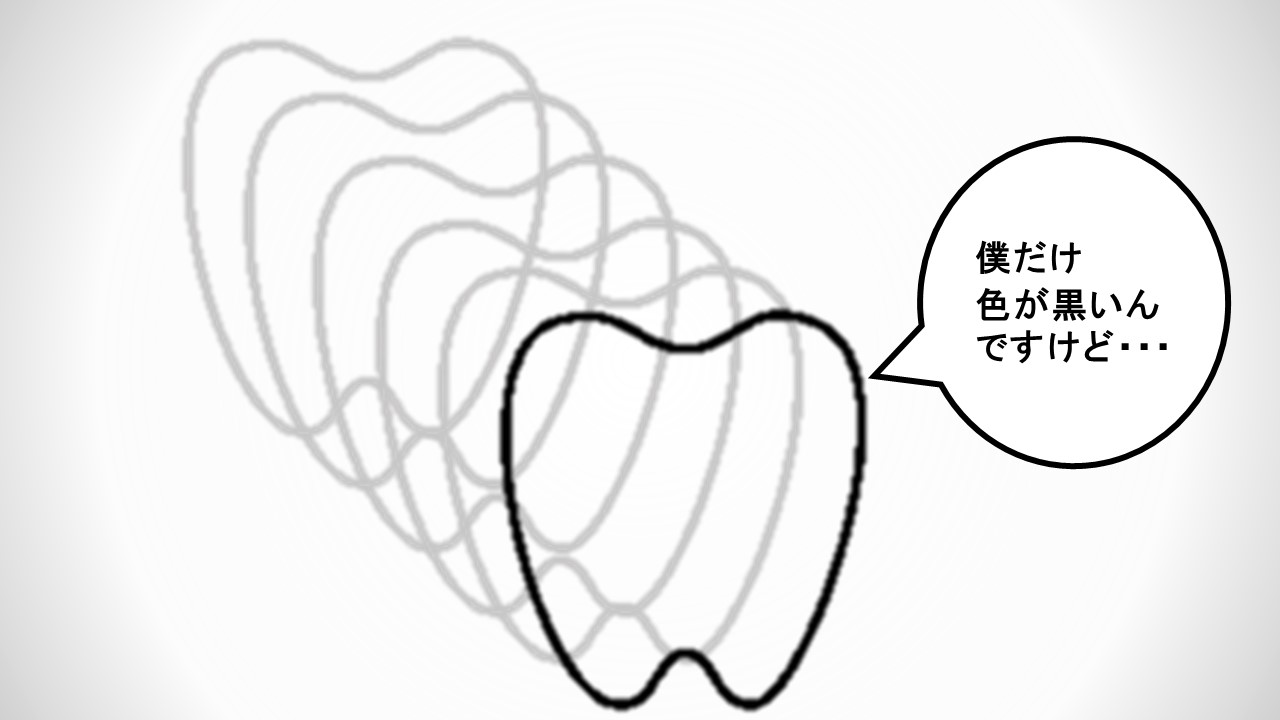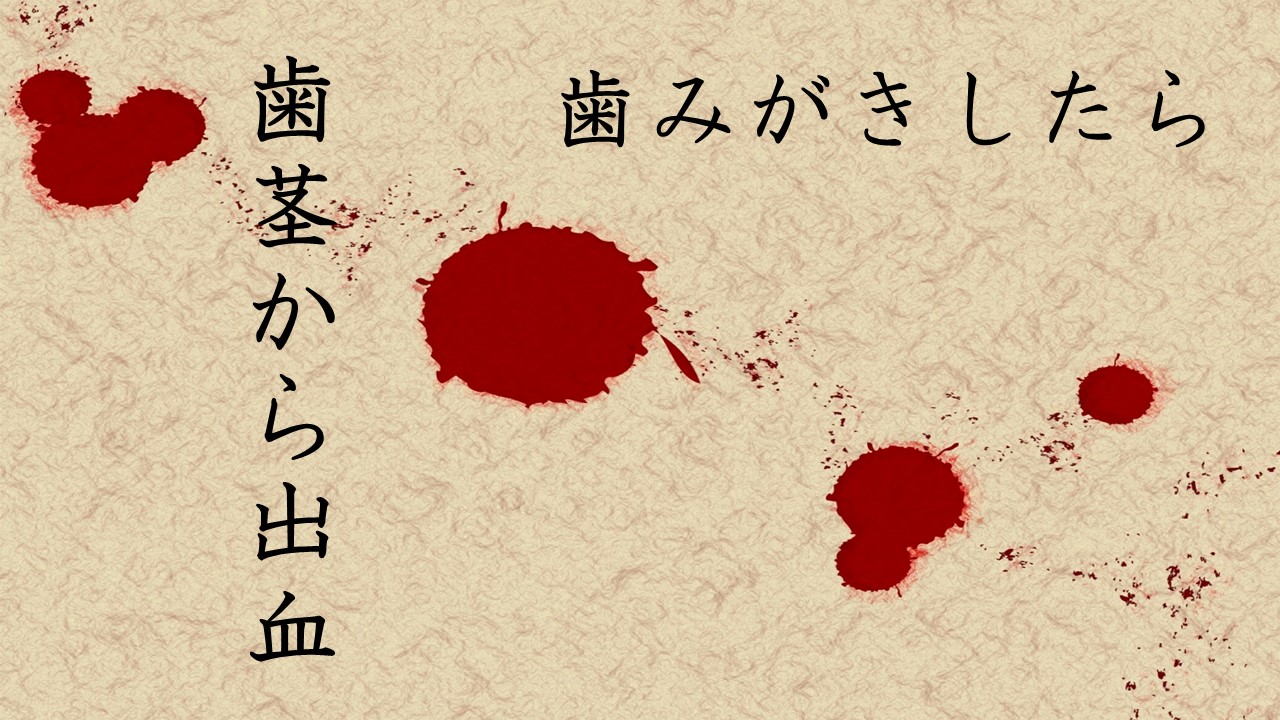顎関節症は、顎の弱くなった現代人の病といわれているぐらいで、多くの方が悩まれているのではないでしょうか?
柔らかい食事が中心となり、噛む力が弱まり、顎関節を支える筋肉が弱まってきたことが、そもそもの原因とも言われています。

「顎関節症」と言っても様々なタイプがあります。
筋肉の障害によるもの
鈍い痛みが特徴で、痛むところを特定しにくく、頬や首・肩など顎関節から離れた部位で痛みを感じる場合もあります。噛むときに使う筋肉(咀嚼筋)が固くなり、動きが悪くなることで、鈍い痛みとなります。
靭帯の障害によるもの
顎を動かす際に、関節部にはっきりとした痛みがあれば、顎関節の靭帯の損傷によるものと考えられます。痛みの感覚としては、捻挫した足を動かすときのような痛みに似ています。
関節円板の障害によるもの
顎関節部には「関節円板」と呼ばれる組織があります。これは、顎関節のクッションの役割をするものです。これが、ズレることで、顎を動かす際に音がしたり、口を大きく開けられなかったりといった症状になります。
変形性関節症によるもの
変形性関節症とは、その名の通り、関節自体が変形してしまっているケース。下顎の関節部分の骨が削れたり新生したりして、関節自体が変形してしまう場合です。症状がない場合もありますし、異音や痛みが伴う場合もあります。
損傷する箇所は上記の4つがありますが、どれか1つではなく、複合的に損傷している場合も多いものです。
「顎関節症かな?」と思ったら、すぐに歯科医に相談しましょう。
現在、「肺炎」が「脳血管疾患」を抜いて日本人の死因第3位になっています。さらに注目すべき点は肺炎による死亡者の96%が65歳以上ということで、高齢者ほど死亡率が上がるということです。

高齢者の肺炎の7割以上は、細菌を含む唾液や食物が気管や肺に入ることで起こる誤嚥性肺炎だと言われています。特に寝たきりや脳血管障害、認知症の患者ほどリスクが高くなります。
これは、嚥下反射(食べ物を飲み込むときに気道が閉じ、食道が開く)や、気道内に異物が入ったときに激しくせき込んで排除する、せき反射が低下して、細菌が気道を通じて肺に入り込みやしくなるためです。
従来、肺炎は発症した場所別に市中肺炎(CAP)と院内肺炎(HAP)の2つのカテゴリーに分けられ、日本呼吸器学会でもそれぞれに対応するガイドラインを作ってきました。しかし、これだけではカバーしきれない新しいカテゴリーとして医療・介護関連肺炎(NHCAP)を2011年に定めています。
医療・介護関連肺炎(NHCAP)とは
次の4つのいずれかに該当する人が発症した肺炎です。
1.長期療養型病床群もしくは介護施設に入所している(精神科病棟も含む)
2.90日以内に病院を退院した
3.介護を必要とする(介護の基準:PS3(限られた自分の身の回りのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす)以上をめどとする)高齢者・身障者
4.通院にて継続的に血管内治療(透析、抗菌薬、化学療法、免疫抑制薬等による治療)を受けている
この予防として注目されているのが口腔ケアです。
歯科医師である米山武義氏の調査報告によると、「介護者が日常的な口腔ケアを毎日行い、歯科医師等が週1、2回の専門的な口腔ケアを実施したグループは、口腔ケアをしなかったグループと比べ肺炎の発症率が39%、死亡率は約53%低かった」と報告しています。

日常的口腔ケアと専門的口腔ケアの徹底は、口腔内の病原菌を減らすだけでなく、口腔への刺激により嚥下機能が回復して、食事が進むようになり、栄養状態が改善します(オーラルフレイル予防)。ひいては免疫力が向上して肺炎の予防につながるというのが定説になっています。
転んで前歯を打った。ボールが顔面に当たった。ご飯を食べてたら・・・。
日常生活の中で、何かの拍子に歯が抜け落ちる事ってたまにあります。
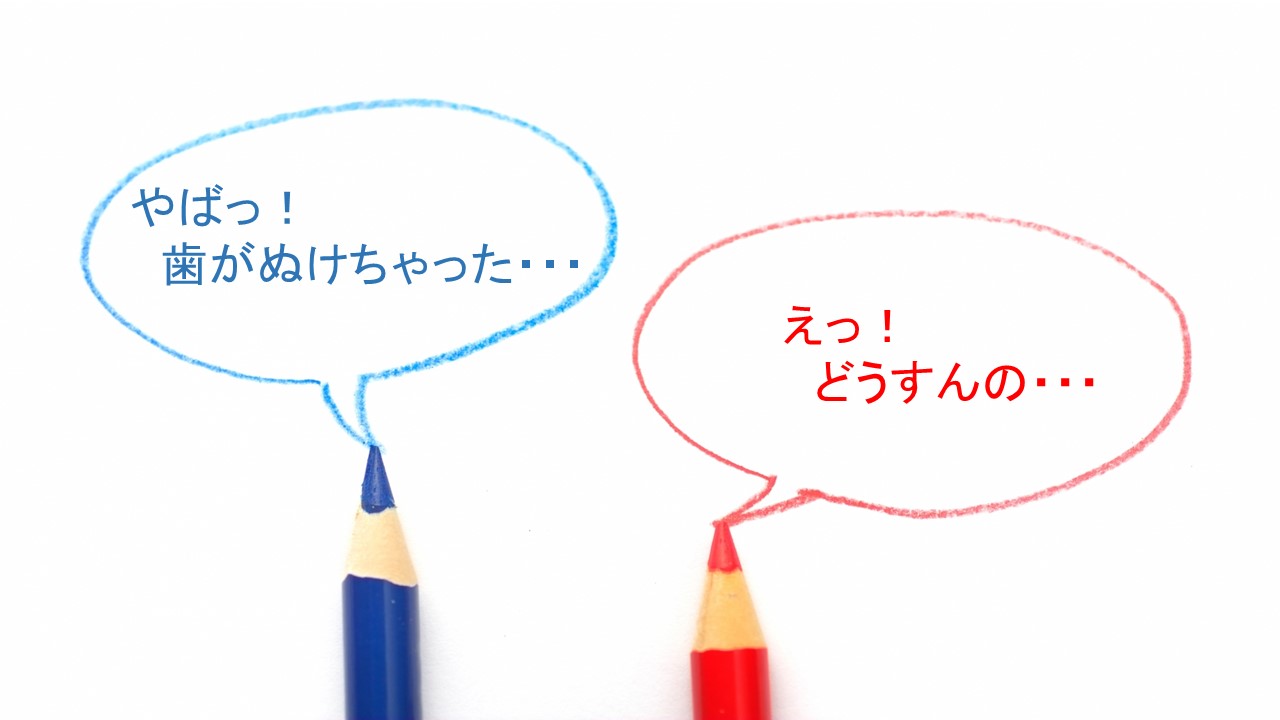
そんな時、歯医者さんに行くまでの対処法について今回はお話します。
抜けた場所の血を止めよう!
歯が抜けた場合に血がでていたらまずは止血を行ってください。ガーゼなどで抜けた箇所を圧迫して血を止めてください。抜けた箇所に血が固まらないようにしましょう。
抜けた歯の保管方法
抜けた歯に、砂や汚れが付着しても、石鹸やアルコールなどを使わずに、流水で洗い流しましょう。その後、元の位置にもどるようなら、抜けた歯の所に差し込みましょう。
戻らない場合は、舌の下に歯を入れて唾液で湿らせるか、生理食塩水につけ歯を乾燥させないようにして歯医者さんに持って行きましょう。
あくまで一時的な応急処置ですので、歯医者に行って治療しましょう。
みなさん、「オーラル・フレイル」という言葉をご存知でしょうか?
「オーラル・フレイル」とは「歯・口の機能の虚弱」
「オーラル・フレイル」とは高齢者の口腔機能低下により虚弱や老衰など介護が必要となる一歩手前の段階のことです。
「食環境の悪化から始まる筋肉減少を経て最終的に生活機能障害に至る構造の研究(東京大学高齢社会総合研究機構の辻哲夫教授、飯島勝矢准教授ら)」で示されました。
高齢期において人とのつながりや生活の広がり、誰かと食事するなどといった「社会性」を維持することは、活動量、精神・心理状態、歯・口の機能、食・栄養状態、身体機能など、多岐にわたる健康分野に関与することが明らかになっています。この「社会性」が欠如していくと、低筋力や低身体機能などの「サルコペニア」(加齢性筋肉減弱症)や低栄養などによる生活機能の低下を招き、ひいては要介護状態に陥ることが懸念されています。

65歳以上の約6人に1人が低栄養傾向の危険に直面。
最新の厚生労働省の調査によると、65歳以上の約6人に1人、85歳を超えると約3人に1人が、低栄養傾向という危険に直面しているそうです。
高齢者においては、口腔機能の低下により、麺などツルッとしたものや軟らかいものばかりを好んだり、果物や生野菜、肉類を食べなくなると、タンパク質やビタミン、ミネラルなどが不足し、固いものや繊維質の多いものを食べるのが難しくなるため、食物繊維が足らなくなるなど、栄養バランスが崩れ、栄養が足りてない「低栄養」状態に陥りやすいのです。

「オーラルフレイル」を病名に
日本老年歯科医学会では「高齢者の口腔機能低下を病名にできるか」を検討しており、その通称に「オーラルフレイル」があります。
「なぜわざわざ病名をつけるの」と思いますよね。
それは、口腔機能低下が顕著になる前の段階で予防することの重要性を様々な医療の現場で認識し、見逃さないことが重要だからです。
また、一般国民自身がより早期の気付きを持って歯科口腔機能の維持・改善に普段から心がけるよう呼びかける目的もあります。
わずかな歯・口の機能の衰えが、身体全体の衰えに繋がっていくので、ささいな歯・口の機能の低下を軽視しないことが大切なのです。
「お茶は万能薬」日本では昔から薬としても使われており、お茶が美容や健康に良いというのは、もう随分前から言われている話ですね。
お茶は血中コレステロールを低下させて、血液をサラサラにしたり、脂肪の吸収を抑えて、肥満を解消する作用も持ち合わせています。
さらに、お茶には虫歯予防や口の病気に対しても効果があるのをご存知でしょうか?

お茶に含まれているカテキンがポイント!!
お茶には、沢山の成分が含まれていて、それぞれ、健康に寄与する方法が異なります。
お茶(緑茶)にはカテキン・ビタミンC・フッ素・フラボノイド・ポリフェノールなど体にいい成分が色々あるのですが、そのなかでも最も注目されているのがカテキンです。
カテキンというのは、細菌やウイルスに対する強い抑制作用を持っています。
お茶に含まれるカテキンが虫歯菌の増殖を抑えてくれるのです。
なお、お茶のカテキンについては多数の研究がありますが、緑茶(特に煎茶)が最も多く含まれているようです。
どうしてカテキンが細菌・ウイルスを抑えるの?
カテキンという物質は、もともとタンパク質にくっつきやすい性質があります。
そして、細菌のカラダというのは、タンパク質で出来ているため、カテキンが付着しやすいのです。カテキンに付着された細菌は、身動きがとりづらくなります。
すると、歯の表面に住み着くことが難しくなり、結果として虫歯の発生を予防してくれるんですね。それに加え、カテキンは歯垢(プラーク)を作る酵素の働きを邪魔する働きも持っています。
ちなみに、ウイルスに対しても、同様のメカニズムでウイルスの増殖を抑えてくれるみたいですね。
鏡で口の中を覗くと、白いはずの歯が黒い・・・・そんな歯ありませんか?
歯は白い組織なので黒い色が付くと目立つもの。
今回は歯が黒くなる原因をピックアップしてみます。
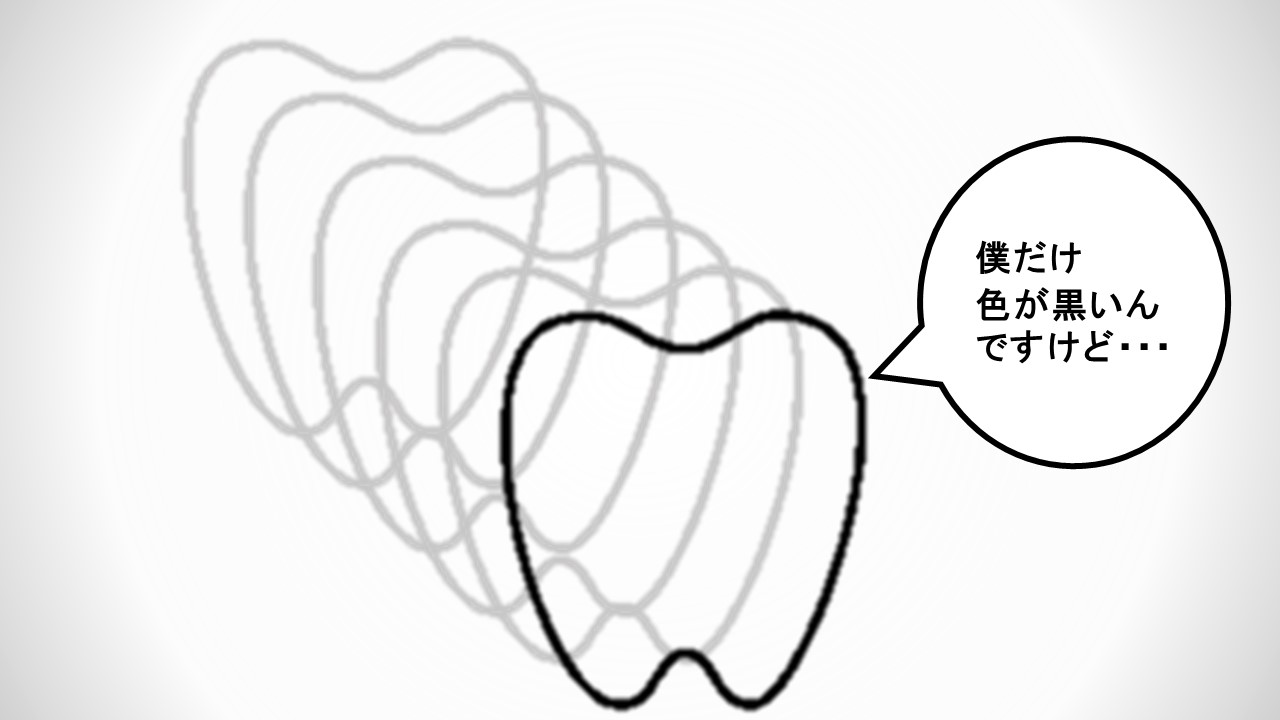
歯が黒くなる6つの理由
歯の神経(歯髄)が死んでいる。
歯をぶつけたり、虫歯などで歯の神経が死んでしまうと、歯は黒くなってきます。
痛みを伴わず、知らないうちに歯の神経が死んでしまうことがあり、ある日突然、鏡を見て驚くことが多いです。こういう場合は、いち早く死んだ神経を取り除く処置をしましょう。
虫歯になっている。
虫歯になると歯が色が黒くなります。虫歯が大きく進行している場合は、削る必要があり、放置していても治ることはありません。また、黒い点が歯についている場合に、小さな虫歯だと思っていても、実は内部で大きく進行している可能性があります。虫歯が進行する前に早期治療を行いましょう。
歯に汚れ(着色・ヤニ)がついている。
歯の着色は、毎日の食事でどんどん蓄積されて、カレーやワインなどの色が強い食べ物は、特に色が付着します。また、タバコのヤニも、着色汚れの大きな原因の一つです。歯科医院でのクリーニングやホワイトニングで綺麗になります。
詰めものが劣化している。
歯の詰め物が劣化すると、黒ずんできます。特に金属の詰めものをしている場合、約3~4年程度で金属イオンが漏れ出して、歯を黒くすることがあります。また、白い詰め物でも劣化してきて、色が変化してきたのであれば、詰めものを詰め直しましょう。
歯石が付着している。
歯ぐきの下に隠れている歯石は黒色で、それらが歯と歯茎の境目から見えるようになると、歯が黒く見えます。歯周病の処置(除石)をしましょう。
抗生物質の影響。
テトラサイクリン系の抗生物質を歯の成長期(妊娠期・幼少期)に服用した場合、抗生物質の影響で歯が黒く変色することがあります。歯科医師に相談しましょう。
皆さん、歯軋りをしていませんか?
夜寝てるときに家族に指摘されたり、仕事中、築いたらギリギリと歯軋りや喰いしばっていたという経験あると思います。
歯軋りや喰いしばりの原因というのは解明されていませんが、やはり今のところ、ストレスが最有力視されています。ストレスが外部からかかることによって、精神的に不安定になり、心を落ち着かせるために歯軋りを行ってしまうようです。
歯軋りをほっておくと、歯を削ったり、歯の被せ物や詰め物を破壊したり、ひどいときには顎関節症を悪化させたりします。

ひとことに「歯軋り」といってもいろんな種類があります。
歯軋りのタイプ
1:グラインディング
歯を横にギリギリとこすり合わせるタイプの歯軋りです。普通、歯軋りと言うと、このタイプを思い浮かべますよね。
2:クレンチング
上と下の歯を強く噛みしめるタイプの歯軋りです。横にスライドさせないので、あまり音が鳴りません。でも、歯にかかる力は相当なものがあります。
3:タッピング
歯をカチカチと噛み合わせるタイプの歯軋りです。よくイライラすると、カチカチ歯を鳴らしてしまう人がいますが、それはこのタイプであると言えます。
歯軋りの治し方
噛み合わせを調整する
上の歯と下の歯の噛み合わせが悪いと、無意識のうちに歯軋りをしてしまうケースがあります。この場合、咬合調整と呼ばれる方法で、正しい噛み合わせに治すことで、歯軋りを取り除くことが可能です。
夜の歯軋りはマウスピースで取り除く!
眠っている間に歯軋りをしてしまっている人には、とても良い治療法があります。それはマウスピースを就寝中にはめて、強制的に歯軋りができなくする治療法です。
ストレスを解消する!
ストレスをいかに逃がしていくか、ということを日常生活の中で工夫していくしかありません。休みの日にリフレッシュして、一気にストレスを発散してしまうというのも一つの方法です。
重症化する前に歯医者さんに相談しましょう!
「歯を磨いていたら、歯茎から血が出た!」という経験がある方は多いのではないでしょうか?
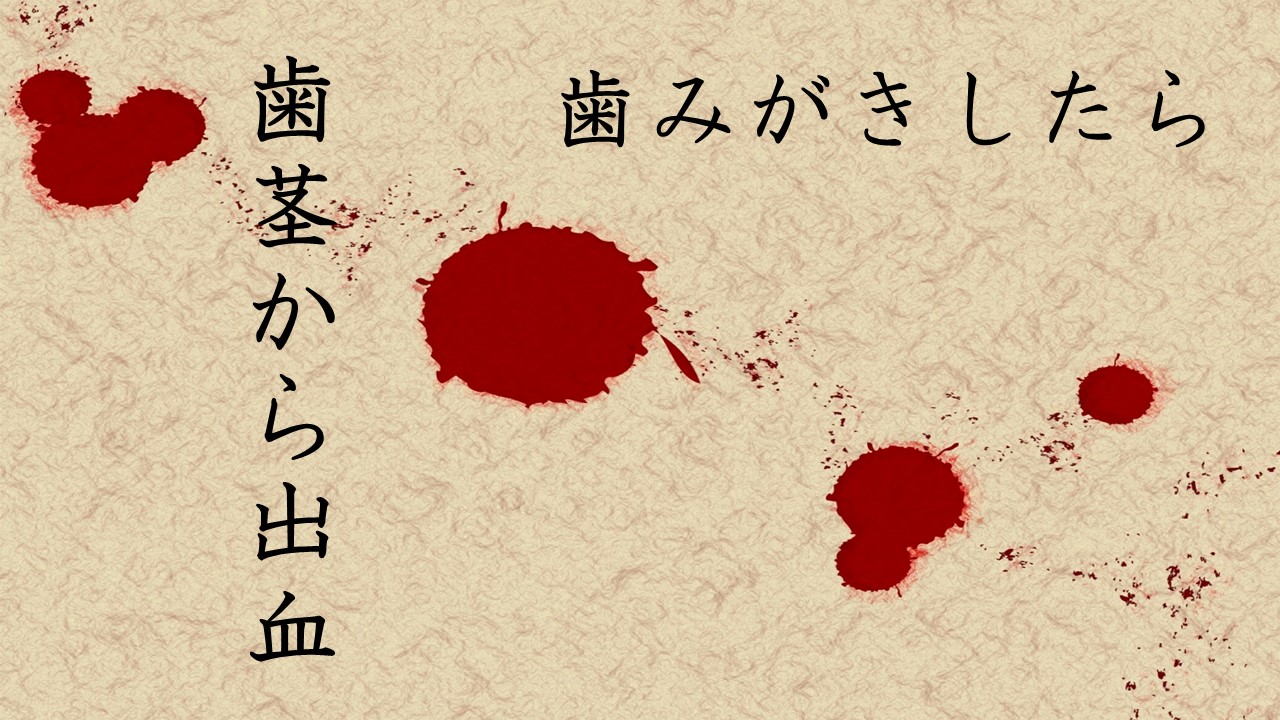
歯みがきの時、歯茎から血が出る原因の90%以上は歯肉炎です。
一時的に出血したのであれば、歯周病の初期状態である歯肉炎の可能性が高いです。
しかし、長期間にわたり出血が続く場合は、他に原因がある場合があります。
その他の歯茎から出血する原因
ホルモンバランスの変化
更年期障害や妊娠など、ホルモンバランスに変化が起こると歯茎から血が出やすくなります。女性ホルモンは体の働きと深い関係があり、ホルモンバランスの変化は歯茎への血流が増加することがあります。ホルモンバランスが変化している時は、歯周病の方が増加する傾向があるので、毎日の歯磨きは怠らないようにしましょう。
ゴシゴシ磨きで歯茎を傷付けている
歯を磨く力が強すぎて、歯茎から血が出ているのかもしれません。口内は敏感なので、歯茎が腫れていなくても、硬い歯ブラシや強すぎる力でのブラッシングは出血を引き起こします。鉛筆持ちで優しく歯ブラシを持ち、小刻みに動かして磨くのが良いです。
薬が原因で歯茎から血が出る
抗凝固剤や降圧剤・抗てんかん薬などは、出血の原因となる場合があります。降圧剤・抗てんかん薬は歯茎を厚くするので、歯周ポケットが深くなる事により、汚れが取りにくくなります。そうなると、歯茎が腫れて、出血を起こす原因になるのです。また、抗凝固剤は、血の流れを良くする薬ですので、出血が止まりにくくなります。
ドライマウスが原因
ドライマウスとは、唾液量が減少して、口内が乾燥してしまう状態の事をいいます。唾液量の分泌が減少すると、汚れを洗い出してくれないので、食べカスが残り、歯茎が腫れて出血を起こします。

一時的な出血なら歯みがきで止めよう
原因が歯肉炎であるならば、出血を恐れずに歯みがきを丁寧にすることで出血は治まってきます。
その際、気を付けなければならないのは
①歯と歯茎の境目にハブラシの毛先を当てて小刻みに動かして磨く。
②毛先がやわらかめのハブラシに変えて、歯茎をマッサージするように優しく磨く。
③デンタルフロス(糸ようじ)や歯間ブラシなども使って落としにくい汚れもしっかり落とす。
出血が治まらない場合は早めに歯医者さんに相談しましょう!
前回は、鋭い歯の痛みに悩まされる、知覚過敏症のメカニズムについてお話しましたね(コラム:どうしてなるの?知覚過敏!!)
今回は、知覚過敏症の治療方法についてお話しします。

歯ブラシの種類を考える。
まず歯ブラシの選択に気を付けましょう。歯ブラシの毛先は、できるだけ柔らかいものを選び知覚過敏になっている歯の部分への刺激を軽くします。注意しなければならないのは、磨くときの強さです。知覚過敏の部分は、歯の表面が薄くなっており歯の神経との距離も近いため、ゴシゴシと強く磨かず、鉛筆持ちで優しく小刻みに歯ブラシを動かして歯を磨きましょう。
もうひとつ大事なポイントは、歯磨き粉です。
市販されている歯磨き粉の多くには、研磨剤が含まれています。本来この研磨剤は、歯垢などのしつこい汚れを落とすのに非常に有効なのですが、歯を削るおそれもあります。出来る限り研磨剤のような成分が入っていない歯磨き粉を使用することが望ましいと言えます。
また、知覚過敏の症状をおさえる成分が入っている、知覚過敏用の歯磨き粉というのもありますので、こちらを使用することをおススメします。
マウスピースで「歯ぎしり」撃退。
「歯ぎしり」が原因となって知覚過敏を引き起こしているタイプの方は、マウスピース(ナイトガード)を寝ている間に装着することによって歯ぎしりを自然に治していきます。
「噛みしめ」が原因となっているタイプの方は、学校や職場で受けるストレスを減らしていくか、解消する方法を考えていきます。場合によっては、昼間用マウスピースを装着し、「噛みしめ」に対応していきます。
知覚過敏用の薬を塗る。
歯科医院では、知覚過敏に効く薬を用意しています。ダメージを受けている歯の表面に、その薬を塗ることで、痛みを抑えます。具体的には、歯の表面をコーティングすることによって、外からの刺激が中の方へ伝わるのを防ぎます。
どうしても治らない場合は神経を抜く。
これら全てに効果がない場合もあります。その時は、痛みを感知する神経自体を抜かなければなりません。少し強引な発想に思えますが、一般的に行われている治療ですのでご安心ください。
知覚過敏症で悩まれている方は、はやめに歯科医師にご相談ください。
歯科医院で治療を受ける時、麻酔を打っても痛みを感じたという方がいるのではないでしょうか?
実は麻酔薬というのは、その日の体調やその人の体質によっても、効き目が大きく異なります。

麻酔が効く過程について
麻酔の注射というのは、歯に痛みを伝える神経に直接麻酔しているわけではないのです。歯茎に注射された麻酔薬は、まず、歯槽骨と呼ばれる骨に浸透していきます。その後、歯の根っこに到達し、よこでようやく歯の神経に麻酔が効き始めます。ですから、ここまでの過程で何か障害があると、麻酔が効きにくくなるという現象が起こります。
こんなケースは麻酔が効きにくい
骨に厚みがあったり、骨密度が高かったりすると、麻酔薬が浸透しにくくなります。下の顎の奥歯などは、とても分厚い骨に覆われているため、もともと麻酔が効きにくい状態にあります。
また、歯や歯茎に強い痛み(強い炎症)がある場合や膿が溜まっているような状態でも、麻酔の効果が炎症によってかき消され、麻酔効果が悪くなります。
あと、麻酔液の種類と患者さんの体質の相性もあります。麻酔液の種類によって効きやすかったり、効きにくかったりする場合もあります。
このように、麻酔薬というのは、誰でも同じように作用するものではありません。その人の体質や体の部分、体調によっても作用の仕方が異なるのです。
以前、麻酔が効きにくかった経過がある人、麻酔でアレルギー反応が出た経験がある人は、治療前に歯科医師にお話しておきましょう。
徳島市 市役所の近くの歯医者です。木曜日もやってます。